研究所について
研究所概要
5部門から編成されており、新しい機能性分子の合成、新しい分子集積の化学、有機・無機融合材料の化学、先端材料の素子化に関する化学など、多岐にわたる研究に取り組むとともに、各分野の研究グループが連携して、原子・分子・ナノスケールからマクロスケールまでの物質の構造と機能にかかわる基礎学術とその応用化に関する研究を推進している。
当研究所は、筑紫地区、伊都地区の二地区に分かれている。大学院総合理工学府、大学院理学府、大学院工学府の協力専攻となっており、それぞれの学府を通じて修士課程、博士課程の大学院生を募集している。
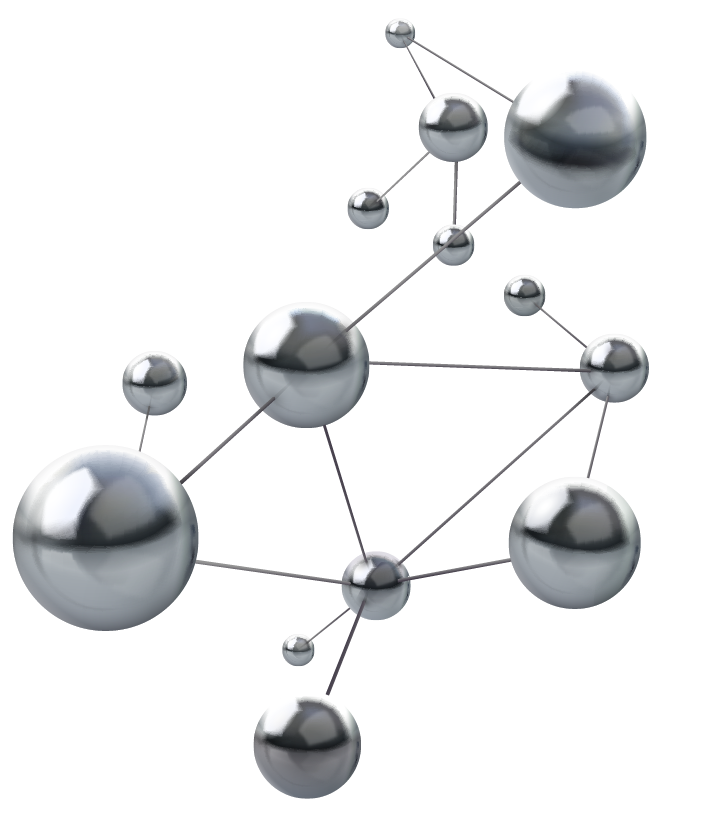
研究内容・特色
- 物質化学の未踏領域である原子集合体(クラスター)、分子集合体、超分子の構造と機能に関する基礎化学を確立し、触媒機能や生体関連機能を持つ分子や集合体の創出を目指す。
- 高次ナノ構造を有するソフトマテリアル、および、その複合体の合成と構造・物性評価をおこない、その特徴を活かして、先端ソフトデバイス、ソフトマシンを創造するとともに、ナノバイオテクノロジーの開拓を目指す。
- 分子ナノテクノロジー、バルク材料の微細加工、自己組織化等の手法を駆使して有機-無機-バイオ、炭素-有機など従来の学問領域の境界に位置する融合材料の創成と応用を目指す。
- 精密に構築された微細構造をもつ新機能物質の創製と機能解析評価を通じて、機能材料の実用基盤の構築を目指す。
- 以上の特徴ある分子、分子・原子集合体、ナノ材料、融合材料の先導的な物質化学領域を創造するとともに、研究成果を、新規デバイス、環境保全材料、環境適応型プロセス、生体適合材料、エネルギー創出・貯蔵材料等、ナノサイエンス・ナノテクノロジーを基盤としたIT、ライフサイエンス、環境・エネルギー分野への展開を図る。
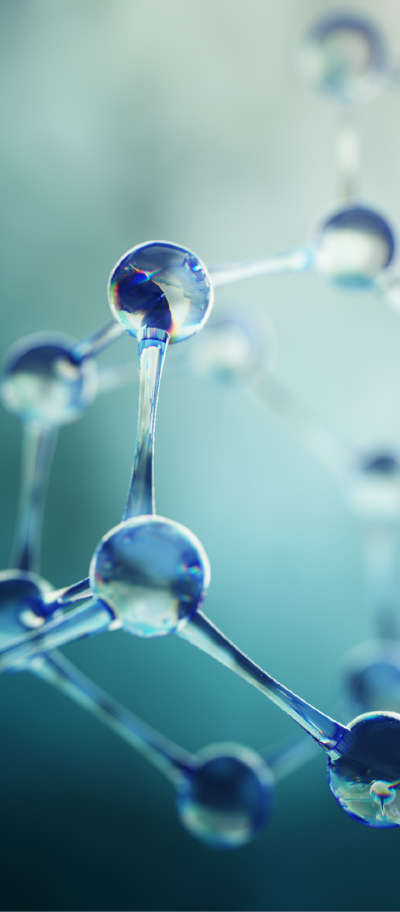
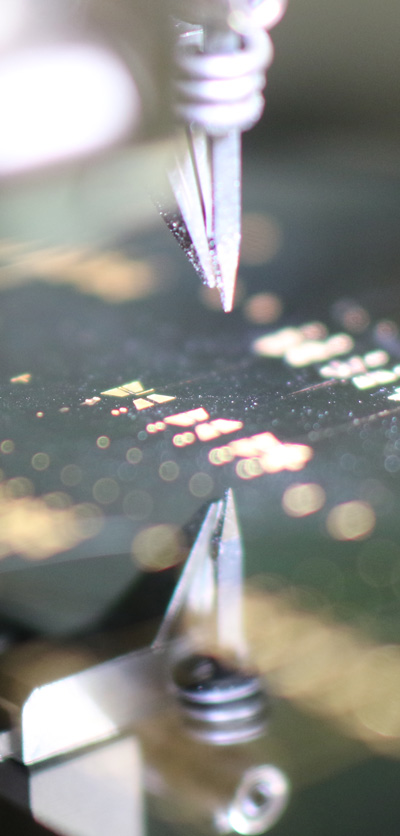
沿革
-
1944年
九州帝国大学木材研究所(3部門)創設。
-
1949年4月
九州大学生産科学研究所(5部門)として再編。
-
1987年5月
九州大学機能物質科学研究所(3大部門(13研究分野)+2客員部門)として再編。
-
1993年4月
九州大学基礎有機化学研究センター(3大部門)創設。
-
2003年4月
九州大学機能物質科学研究所と同有機化学基礎研究センターを融合・改組して、先導物質化学研究所を設立。
-
2010年4月
物質・デバイス領域共同研究拠点(ネットワーク型共同利用・共同研究拠点)に認定される。
-
2014年4月
ソフトマテリアル部門創設。
刊行物
要覧
先導物質化学研究所の年次要覧(PDF)がダウンロードできます

